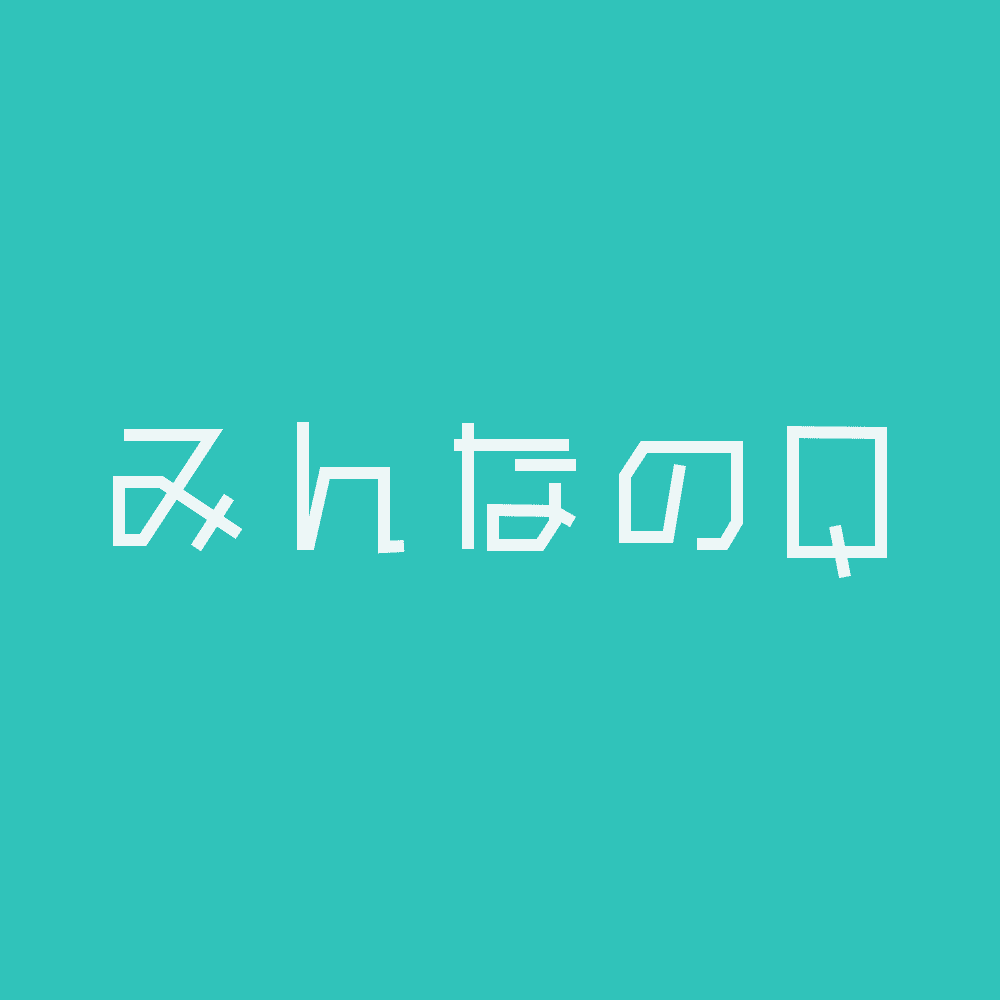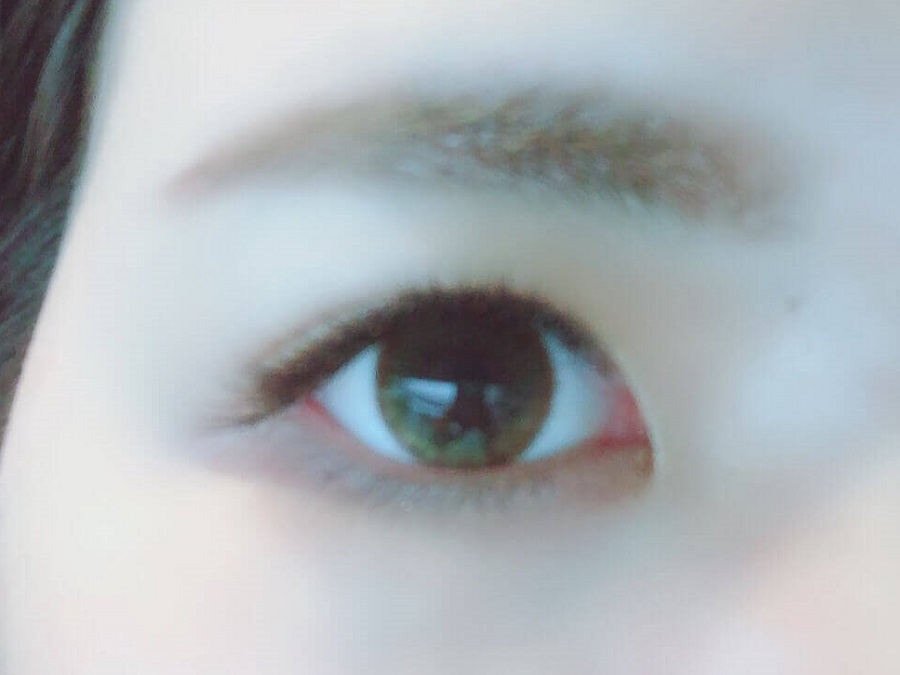香典の由来
葬儀の際には香典を持参してお渡しするのが一般的になっていますが、これは昔から伝えられる助け合いの精神が現在にも受け継がれている名残だとされています。
昔は貧しくてお金がなく、葬儀を出せない人が多かったため、周囲の人達で少しずつお金を出し合ってお互い様という気持ちで香典を渡していたのが始まりだったという説もあります。
現在でも知人の訃報を聞きつけたら、通夜か葬儀のどちらかに香典を持参するのが一般的です。
ただ香典袋に入れて渡せば良いという考えではなく、きちんと先方の宗教や宗派に合わせたマナーを守るようにしてください。
香典の渡し方
どのくらいの金額を渡すのが相応しいのか迷う方も多いですが、故人または遺族との付き合い方に応じて5千円か1万円を渡すのが一般的です。
ご自身の年齢や社会的な立場も考慮しながら適切な金額を用意してください。
この時、新札は入れないようにするのが正しいマナーですが、どうしても新札しか用意できなかったという場合には自分で折り目をつけてから入れてください。
香典は袋にお金を入れたまま渡すのではなく、きちんとふくさに包み持参しましょう。
不祝儀袋の用意
香典は不祝儀袋に入れて渡すことになりますが、宗教や宗派によって適さない図柄や表書きが存在しているので、必ず先方が信仰している宗教を確認しておきましょう。
不祝儀袋にハスの花が印刷されているものについては、仏教式の葬儀にしか使用できません。
表書きについては御霊前、御仏前など色々ある中で御霊前に関してはどの宗教でも使えるとされていますが、実際のところは浄土真宗以外の仏教はOKだと考えてください。
浄土真宗の場合は亡くなってすぐ仏様になるという教えのため、霊になるとの考えが存在しないことから、御仏前が正しいです。
どの仏教でも活用できる表書きとしては、御香奠や御香料がおすすめです。
紙式の場合でも御霊前を使うことができますが、御玉串料、御榊料なども活用できます。
ハスの花ではなく、白百合や十字架が印刷されている不祝儀袋についてはキリスト教用になります。
キリスト教でも御霊前は使えますが、一般的には献花料、御花料などの表書きにすることが多いです。
カトリックの場合は御ミサ料でも構いませんが、プロテスタントの場合はNGになるためどちらかわからない場合には使用しない方が良いでしょう。
なお、地域によっては香典の受け取りを辞退される場合があります。
特に関西圏では故人の意思などが理由で香典を辞退する事例が増えているそうなので、辞退された場合には無理やり押し付けるような真似は避けてください。
どうしてもという場合には、供花やお供え用のお菓子などを持参しましょう。
香典返しのマナー
香典をお渡しする側はもちろん、香典を受け取った側もマナーをきちんと守ってお返しをします。
香典返しを贈るタイミングや相場、品物など相手に失礼のないようにすることが大切です。
最近では、特定の品物を贈った場合に先方の好みが合わなかったというトラブルを避けるため、カタログギフトを選ぶ方が増えています。
※香典返しにおすすめのカタログギフト【マイプレシャスのカタログギフト】
マイプレシャスのカタログギフトなら、お返しの相場が幅広く、簡単なメッセージカードを添えることができるので、気持ちを伝えやすいというところもポイント。
商品だけではなく、香典返しについてのコラムも掲載されているので、そもそも香典返しとは?という部分も確認できます。
こちらも、宗派などによって状況が異なるので、あくまで参考としての検討をおすすめします。